ALPの基準値は?
男女とも 38~113 U/L (共用基準範囲)
※共用基準範囲は日本臨床検査標準評議会(JCCLS)が設定した日本国内の医療機関
で共通して利用されている基準範囲です。
ほとんどの病院がこの基準範囲を設定していると思いますが、病院の方針によっ
ては独自の基準範囲定めている場合もあります。
ALPが高いor低いとどうなの?
高値:肝疾患(肝炎、肝硬変、胆管の障害など)
骨疾患(骨粗しょう症、骨折の回復期、骨肉腫、ビタミンD欠乏など)
成長期の子ども:成長による骨の活発な代謝で自然に高くなることもあります。
妊娠中:胎盤から分泌されるALPにより一時的に上昇すること
低値:低栄養状態(特にたんぱく質不足)甲状腺機能低下症 亜鉛欠乏症
先天的な酵素異常(まれ)
ALPの値に影響を与える要因は?
EDTAやクエン酸塩など抗凝固剤の混入:ALPは低値となります。主にEDTAは血球数測定、クエン酸塩は凝固検査に使用される採血管に含まれている抗凝固剤です。これらは採取した血液が凝固しないようにカルシウムなどを取り除きます。ALPは活性を示すために亜鉛やマグネシウムを必要としますが、それらも取り除かれてしまいALPは低値となる。
ALP(アルカリフォスファターゼ)とは?
ALPは、主に肝臓・骨・小腸・腎臓などに存在する酵素で、体の中の「リン酸化合物」を分解する働きを持っています。特に、肝臓や骨で活発に働いているので、これらの臓器に異常があると数値に変化が出やすいのが特徴です。
まとめ
ALPは、肝臓や骨の状態をチェックするための重要なヒントです。
数値が高くても低くても、「今、体に何が起きているのか?」を教えてくれるサインだと考えて、健康診断の結果を活用しましょう。定期的な検査で、自分の体と上手につきあっていきたいですね。

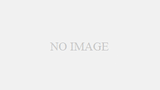
コメント